2025.05.03
東北支部 フレキシブル同好会報告
東北支部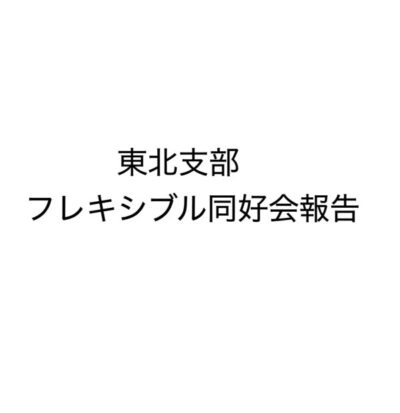
報告者:櫻谷 務
東北支部には、ユニークなフレキシブル同好会があります。全国最小支部(会員数36)ならではの発想から生まれた、同趣・同好をキーワードに不定期に少人数で集まる会です。運営は、企画から実施・報告まで発案者が幹事になって行います。開催目標は年数回程度で、支部行事開催時に併せて効率的に行おうとしています。今年度は、特に豊友会設立40周年記念行事の東北版として「会員講師による小集会」を考えています。記念すべき第1回目が春季総会時に行われましたので報告します。
日 時:2025年4月22日(火)
テーマ: 「森の不思議」
講 師: 支部理事 亀井利光さん (宮城県森林インストラクター資格保有)
内 容(抜粋):
フキノトウ・カタクリ・トウゴクサイシン・マムシグサなどについて大変興味深く為になるお話を聞く事が出来ました。とくに面白く興味深かった事を紹介します。

フキノトウ→ 雄株と雌株があって、雄株には雄しべと雌しべはあるものの、雌しべは機能せず雄しべが花粉を出す。雌株には雌しべしかなく、受粉後花茎を伸ばす。フキの花茎は薹と呼ばれる。フキには、肝毒性のピロリリジンアルカロイドを含むので茹でたあと水にさらす必要あり。「薹が立つ」とは、フキの花茎が伸びてしまい食べ頃を過ぎてしまった状態なのであまりいいイメージで捉えられないが、実は美味との事で驚きました。
カタクリ→ 花には密標なる部分があって虫を寄せる虫媒花。カタクリの一生は約20年で、花が咲くまで8年かかるとの事でビックリ。種子には蟻が好むエライオソームが含まれていて、種子を巣まで運ぶ、言わばエライオソームという賃金でアリに遠くまで運んでもらっている事になるようです。
トウゴクサイシン(はじめて聞く名前でした)→ 山地のやや湿った場所に生える多年草ですが、花が独特です。興味深かったのは、アゲハチョウの祖先と言われるヒメギフチョウとの関係でした。トウゴクサイシンの葉には、毒がありますがヒメギフチョウ幼虫のみが耐性を持つそうです。
マムシグサ→ 茎の部分が毒蛇のマムシの模様に似ているから付いた名前のようです。雌雄異株で雄花の下部には穴があるが雌花にはない、つまりハエは雄花の下にある穴を抜けて雌花へ飛んでいき体につけた花粉を雌しべへ運ぶ。雌花の下部に穴がないので雌花に一度入り込むとハエは抜け出せない仕組みになっているようです。
今回、「会員講師の小集会」の第1回目でしたが、まさに「森の不思議」の一端を紹介して頂きました。2回目以降も楽しみですが、少なくとも発想当時の理事会メンバー9名のテーマは次に控えています。
次のステップとして、理事会メンバー以外の会員の皆様へのテーマ募集です。実はここだけの話ですが、数名有力候補はいらっしゃいます・・・・乞うご期待。次の報告をお待ちください。
私が聴講しての感想は、家族との会話の話題になった事、そして実物を見て確認してみたい衝動に駆られ、これから野山への外出機会が増えそうなこと、そしてもっと知りたいという検索意欲が掻き立てられた事です。
担当 下野 予理一
